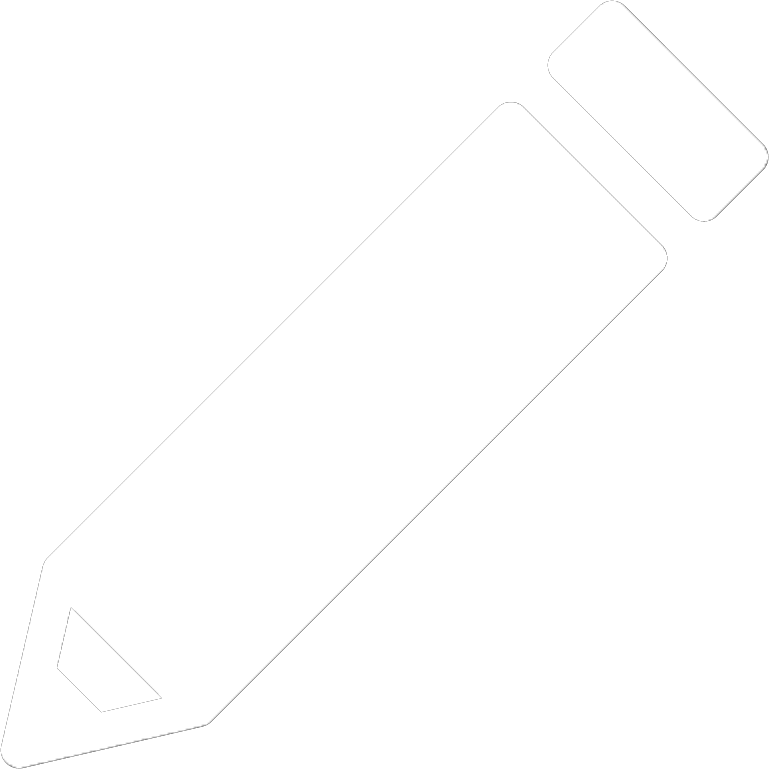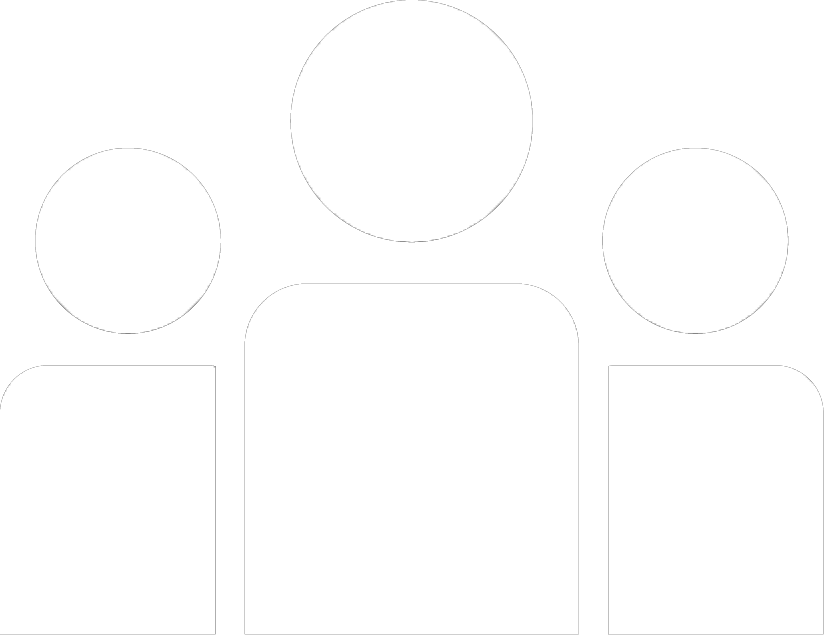「毎日歯磨きしているのに…」その虫歯、食事が原因かも? 論文データで読み解く“科学的に正しい”予防の食事法
「毎日ちゃんと歯磨きをしているのに、なぜかすぐに虫歯になってしまう」
「子供のおやつ、甘いものを控える以外に何を気をつければいいの?」
日々の診療の中で、患者様からこのような切実なご相談をいただくことがよくあります。もちろん、歯ブラシやフロスを使った「プラークコントロール(歯垢除去)」は非常に大切です。しかし、実はそれと同じくらい、あるいはそれ以上に虫歯のリスクを左右する重大な要因があります。
それが、毎日の「食生活」です。
虫歯は、単に運が悪いからなるのではありません。お口の中の細菌(ミュータンス菌など)が、私たちが食べたもの、特に糖分をエサにして「酸」を作り出し、その酸が歯を溶かすことで発生します。つまり、毎日の食事が虫歯菌にとっての「燃料」になってしまっている可能性があるのです。
では、具体的にどのような食事がリスクを高め、逆にどのような食事が歯を守ってくれるのでしょうか?
今回は、「甘いものはダメ」といった曖昧なアドバイスではなく、世界中の最新の研究論文やシステマティックレビュー(世界中の質の高い研究を集めて分析した、信頼性の高い科学的根拠)に基づいた、「本当に歯を守るための食事法」について詳しく解説していきます。
1. 最大のリスク要因:「見えない砂糖」と「超加工食品」
食生活と虫歯の関係を考える上で、避けて通れないのが「糖類」の問題です。特に近年、世界保健機関(WHO)が警鐘を鳴らしているのが「遊離糖類(ゆうりとうるい)」という存在です。
WHOが警告する「遊離糖類」とは?
「遊離糖類(フリーシュガー)」とは、料理やお菓子作りの際に加えられる砂糖だけでなく、ハチミツやシロップ、そして一見健康そうに見える「100%果汁」などに元から含まれている糖類の総称です。
WHOは、虫歯予防のためにこの遊離糖類の摂取量を厳しく制限することを推奨しています。具体的には、1日の総エネルギー摂取量の10%未満に抑えることに加え、さらに5%未満(ティースプーン数杯程度)に抑えることで、虫歯のリスクをより確実に減らせるという科学的データが示されています。
以前は「5%未満」という厳しい目標に対する根拠は限定的でしたが、近年のシステマティックレビューにより、この目標値の重要性を裏付ける証拠がより強固なものとなりました。つまり、生涯自分の歯を守り抜くためには、私たちが思っている以上に「砂糖の量」をシビアにコントロールする必要があるのです。
現代人を狙う「超加工食品(UPF)」の罠

では、私たちはどこからこの「遊離糖類」を摂取してしまっているのでしょうか? その最大の供給源の一つが、「超加工食品(UPF)」と呼ばれる食品群です。
これは、スナック菓子、清涼飲料水、菓子パン、カップ麺、インスタント食品など、工業的に高度に加工され、保存料や添加物が多く含まれる食品のことを指します。
子供や若者を対象とした大規模なデータ分析によると、この超加工食品を多く食べるグループは、そうでないグループに比べて、虫歯になるリスクが1.5倍〜1.7倍も高いことが判明しました。
なぜ、超加工食品はこれほどまでに歯に悪いのでしょうか? その理由は「砂糖が多いから」だけではありません。実は、これらの食品には、食感を良くするために「加工デンプン」が多く使われています。この加工デンプンは、一般的なデンプンよりも歯にネバネバとくっつきやすく、お口の中に長時間留まる性質があります。
つまり、超加工食品を食べるということは、「高濃度の砂糖」と「歯にへばりつくデンプン」という、虫歯菌にとって最高の燃料を長時間お口の中に提供し続けているのと同じことなのです。
2. 砂糖だけじゃない!意外と知らない3つの「虫歯の入り口」
「甘いものを控えているのに虫歯になる」という方は、砂糖以外の要因を見落としているかもしれません。科学的な視点から見ると、以下の3つのポイントも非常に重要です。
① デンプンの「質」と「調理法」
ご飯やパン、イモ類に含まれるデンプン(炭水化物)も、虫歯菌のエサになりますが、そのリスクは調理法によって変わります。
例えば、全粒穀物のような精製されていないデンプンは虫歯のリスクが低いとされています。しかし、先ほど触れた加工デンプンや、加熱調理され糊化(こか:デンプンが糊状になること)したデンプンは、砂糖ほどではないものの、虫歯の原因となることが動物実験などで示されています。
特に、クッキーやビスケットのように「加熱されたデンプン」と「砂糖」が組み合わさった食品は、リスクが高まるため注意が必要です。
② 酸性飲料による「酸蝕症(さんしょくしょう)」
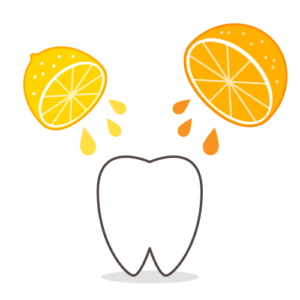
これは虫歯菌による「虫歯」とは別のメカニズムですが、現代人に急増している深刻な問題です。
虫歯が「細菌が出す酸」で歯が溶けるのに対し、酸蝕症(さんしょくしょう)とは、コーラなどの炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘系のジュース、エナジードリンクなどに含まれる「強い酸」によって、歯の表面のエナメル質が化学的に溶けてしまう状態を指します。
市販の多くの飲料は、歯が溶け始める酸性度(pH5.5以下)を大幅に下回っています。ある研究では、スポーツドリンクやエナジードリンクは、炭酸飲料以上に歯の表面を深く溶かすリスクがあることも報告されています。
恐ろしいのは、酸蝕症で歯の表面が荒れると、そこに虫歯菌がより付着しやすくなることです。つまり、酸性飲料の多飲は、歯を直接溶かすだけでなく、将来的な虫歯のリスクも跳ね上げてしまう「二重の危険」をはらんでいるのです。
③ 「だらだら食べ」と「停滞性」

何を食べるかと同じくらい重要なのが、「いつ、どう食べるか」です。
食事をすると、お口の中は酸性に傾き、歯が溶けやすい状態(脱灰)になります。その後、唾液の力で時間をかけて中性に戻り、溶けかけた歯が修復(再石灰化)されます。
しかし、間食が多く、常に何かを口にしている「だらだら食べ」の状態では、お口の中が中性に戻る暇がありません。厚生労働省も、虫歯予防のためには「砂糖の総量を減らす」ことと同時に、「摂取回数を減らす」ことが極めて有効であると発信しています。
また、キャラメルやドライフルーツのように、歯の溝に物理的にくっついて残りやすい(停滞性がある)食品も要注意です。これらは唾液で洗い流されにくいため、長時間にわたって酸が作られ続けます。
3. 年代別:ここだけは押さえたい「ライフステージ別リスク」
虫歯のリスクは、年齢やライフスタイルによって変化します。ご自身やご家族の年代に合わせて、特に注意すべきポイントを確認しましょう。
【乳幼児期】寝る前のミルクと「哺乳瓶」
3歳以下の小さなお子様に発生する虫歯(乳幼児う蝕:ECC)には、特有の原因があります。複数の研究データを統合した分析によると、最強のリスク要因は「授乳・食事の方法」と「砂糖摂取」でした。
特に注意が必要なのが、乳歯が生え始めた後の「夜間の授乳」や「寝ながらの授乳」です。寝ている間は唾液の分泌が激減するため、母乳やミルクに含まれる糖分がお口の中に停滞し、特有の虫歯症状を引き起こすことがあります。
また、哺乳瓶にジュースやイオン飲料を入れて飲ませる習慣も、長時間、高濃度の糖分に歯をさらすことになるため、極めてリスクが高い行為です。
【学童期】100%ジュースと「就寝前」の習慣
小学生くらいの時期(6〜12歳)において、虫歯リスクと強く関連していたのは以下の3点です。
- 100%ジュースの毎日の摂取
- 週1回以上のキャンディ・飴の摂取
- 就寝前の甘い飲み物
「100%ジュースなら健康的」と思われがちですが、歯にとっては「糖分」と「酸」の塊であることに変わりはありません。毎日の水分補給は、お水やお茶に切り替えることが推奨されます。
【高齢期】歯茎下がりと「根面う蝕」

年齢を重ねると、歯周病や加齢によって歯茎が下がり、本来は歯茎の中に隠れていた「歯の根っこ(象牙質)」が露出してきます。この部分はエナメル質よりも柔らかく、酸に弱いため、ここにできる根面う蝕(こんめんうしょく:大人の虫歯)が大きな問題となります。
高齢になると、噛む力が弱くなることから、パンや麺類、煮込み料理など、柔らかい食事を好む傾向が出てきます。しかし、こうした柔らかい食品は歯の根元にネットリと付着しやすく、気づかないうちに根面う蝕を進行させてしまいます。
ご高齢の方こそ、食後のケアや、お口の中に食べかすを残さない工夫が重要になってくるのです。
4. 歯を守る!積極的に摂りたい「予防の味方」
食事はリスクになるだけではありません。選び方次第で、歯を強くし、虫歯を防ぐ味方にもなります。
① 乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルト)

牛乳やチーズ、無糖のヨーグルトなどの乳製品は、「虫歯予防食品」となる可能性があります。その理由は3つあります。
- 再石灰化の促進: 歯の材料となるカルシウムとリンが豊富に含まれています。
- 酸の中和: 食後のお口の中の酸性状態を中和する働き(緩衝能)があります。
- 歯の保護: カゼインなどの乳タンパク質が歯の表面に吸着し、酸から守るバリアのような役割を果たします。
特にチーズは、食後にひとかけら食べることで、お口の中を中性に戻す効果が期待できます。
② フッ化物(フッ素)の活用
フッ化物は科学的に最も信頼性の高い予防成分です。歯の質を強化し、溶け出したミネラルを元に戻す再石灰化を強力にサポートします。
フッ素配合の歯磨き粉を使うのはもちろんですが、海外のデータでは、水道水などに適切な濃度のフッ素が含まれている地域では、子供から大人まで虫歯の発生率が明らかに低いことが分かっています。日本においても、フッ素入りの洗口液や歯科医院でのフッ素塗布を定期的に行うことで、食事によるダメージをリセットする手助けになります。
③ 代用甘味料(キシリトールなど)
「甘いものがやめられない」という方の救世主が、キシリトールなどの代用甘味料です。キシリトールは、虫歯菌がエサとして利用できないため、「虫歯の原因にならない(非う蝕原性)」甘味料として知られています。
最近の研究では、キシリトールそのものの虫歯予防効果については「エビデンスの質が低い」とする報告もありますが、少なくとも「砂糖の代わりに食べる」ことで、リスクをゼロにできる点は非常に優秀です。
5. 最先端の研究:食事と「お口の細菌バランス」
最後に、最新の研究トレンドについても少し触れておきましょう。最近の歯科研究では、特定の食べ物だけでなく、食事が「お口の中の生態系」に与える影響が注目されています。
私たちのお口の中には、腸内フローラと同じように、膨大な数の細菌が住んでおり、これを「口腔マイクロバイオーム」と呼びます。
健康な状態では、善玉菌と悪玉菌がバランスを保っていますが、糖質の多い偏った食事や喫煙などが続くと、このバランスが崩れて悪玉菌が暴走する「ディスバイオシス(細菌叢の破綻)」という状態に陥ります。これが虫歯や歯周病の根本的な原因となるのです。
最近では、このバランスを整えるために、乳酸菌などの「プロバイオティクス(生きた善玉菌)」や、さらに新しい「ポストバイオティクス(菌の代謝産物)」を利用して、虫歯菌の活動を抑えようという研究も進んでおり、次世代の予防法として期待されています。
まとめ:今日からできる「歯を守る食事」のルール
今回の科学的根拠に基づいた「虫歯にならないための食事法」をまとめると、以下のようになります。
- ☑砂糖の総量を減らす: 特にジュースや超加工食品など、「見えない砂糖」に注意する。
- ☑回数を決める: 「だらだら食べ」はやめて、おやつは時間を決めて一度に食べる。
- ☑酸に気をつける: 酸っぱい飲み物をチビチビ飲むのは避ける。
- ☑味方を増やす: 食後にチーズを食べたり、おやつをキシリトールに変えたりする。
- ☑寝る前は水だけ: 就寝中は歯が無防備になるため、寝る前の飲食は絶対に避ける。
虫歯は「削って詰める」だけでは治りません。その原因となっている「生活習慣」を変えない限り、何度でも再発してしまう病気です。
「自分にはどんなリスクがあるの?」「子供には具体的に何を食べさせればいい?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、歯科医院で相談してみてください。
毎日の歯磨きと、賢い食事の選択。この2つの柱で、一生使える大切な歯を守っていきましょう。
中村歯科の矯正治療について
当院は、インビザライン治療において3年連続で「ブルーダイヤモンドプロバイダー」として表彰されています。豊富な実績と経験に基づき、患者様一人ひとりに最適な治療プランをご提案いたします。
当院の矯正治療の特徴:
- 「インビザライン」「Smartee(スマーティー)」「イーラインスマイル」の3種類のマウスピース矯正から選べる多様な選択肢
- 部分矯正から全顎矯正、外科矯正まで幅広く対応可能
- 抜歯を極力避け、顎の位置を改善することで顔立ちにもアプローチする先進的な「SmarteeGS」を導入
- ホワイトエッセンス加盟院のため、矯正と同時にホワイトニングも可能
歯並びや噛み合わせでお悩みの方は、まずは無料相談へお越しください。
参考文献・引用元
- ・Moynihan PJ, Kelly SAM. Effect on caries of restricting sugars intake: systematic review to inform WHO guidelines. J Dent Res. 2014;93(1):8-18.
- ・Cascaes AM, da Silva NRJ, Fernandez MDS, Bomfim RA, Vaz JDS. Ultra-processed food consumption and dental caries in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr. 2022;128(9):1-10.
- ・Sandy LPA, Helmyati S, Amalia R. Nutritional factors associated with early childhood caries: A systematic review and meta-analysis. Saudi Dent J. 2024;36(3):413-419.
- ・Mahboobi Z, Pakdaman A, Yazdani R, Azadbakht L, Montazeri A. Dietary free sugar and dental caries in children: A systematic review on longitudinal studies. Health Promot Perspect. 2021;11(3):271-280.
- ・Gkavela G, Pappa E, Rahiotis C, Mitrou P. Dietary Habits and Caries Prevalence in Older Adults: A Scoping Review. Dietetics. 2024;3(3):249-260.
- ・Heasman PA, Ritchie M, Asuni A, Gavillet E, Simonsen JL, Nyvad B. Gingival recession and root caries in the ageing population: a critical evaluation of treatments. J Clin Periodontol. 2017;44(Suppl 18):S178-S193.
- ・Herod EL. The effect of cheese on dental caries: a review of the literature. Aust Dent J. 1991;36(2):120-125.
- ・National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements. Fluoride: Fact Sheet for Health Professionals . Bethesda (MD): National Institutes of Health;
- ・Heidari F, Heboyan A, Rokaya D, Fernandes GVO, Heidari M, Banakar M, et al. Postbiotics and Dental Caries: A Systematic Review. Clin Exp Dent Res. 2025;11(1):e70114.
■SmarteeGS矯正(スマーティージーエスきょうせい)
【治療内容】
カスタムメイドで制作されたマウスピースを定期的に交換しながら少しずつ歯に適切な力をかけて歯並びを整えていく矯正治療です。
【標準的な費用(自費)】
矯正治療費
相談・検査・診断料 無料
調整料 無料
SmateeGS(マウスピース矯正)1,430,000円(税込)
【治療期間及び回数】
症状や治療方法によりますが、一般的に2年前後の治療期間となる方が多いです。通院回数は2〜3ヶ月に1回です。
【副作用・リスク】
・マウスピースの装着時間が少ないと治療期間が長引く可能性があります。
・他の矯正治療法と同様に、疼痛・歯根吸収・歯肉退縮の可能性や適切な保定をしないと治療後に後戻りすることがあります。
【医薬品医療機器等法(薬機法)に関する記載事項】
・薬機法上の承認/認証(以下「薬事承認等」という。)を得ていない医療機器、医薬品であること
当院で扱うマウスピース型矯正装置(Smartee GS)(スマーティージーエス)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)において承認されていない医療機器になります。
・当該医療機器又は医薬品の入手経路
当院で扱うマウスピース型矯正装置(Smartee GS)(スマーティージーエス)は、中国にあるShanghai Smartee Denti-Technology Co., Ltd.から個人輸入により入手しております。
・当該医療機器又は医薬品と同一の性能又は同一の成分の他の医療機器又は医薬品で薬事承認等を得ているものの有無
マウスピース型矯正装置はSmartee GSの他に様々な種類があり、その中には国内で薬事承認されているマウスピース型矯正装置もございます。
・当該医療機器又は医薬品の諸外国における安全性等に係る情報
マウスピース型矯正装置(Smartee GS)(スマーティージーエス)は中国において医療機器承認を取得している医療機器になります。Smarteeのマウスピース型矯正装置は世界47カ国以上で、これまでに1,000,000人を超える症例数がある治療です。(うちSmartee GSは83,000人、2024年12月時点)マウスピース型矯正装置(Smartee GS)の使用により指摘される具体的なリスクは歯根吸収、歯肉退縮、装置の紛失・破損、不快感、咬合不調和、虫歯や歯周病のリスク、アレルギー反応、発音障害、治療延長、顎関節症の悪化となります。
・当該医療機器又は医薬品を用いた治療には医薬品副作用被害救済制度の対象とならないこと
マウスピース型矯正装置(Smartee GS) の使用により万が一重篤な副作用が生じた場合には、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
■インビザライン
【治療内容】
カスタムメイドで制作されたマウスピースを定期的に交換しながら少しずつ歯に適切な力をかけて歯並びを整えていく矯正治療です。
【標準的な費用(自費)】
矯正治療費、相談・検査・診断料 無料、調整料 無料
インビザライン(マウスピース治療)
264,000円〜899,800円(税込)
【治療期間及び回数】
症状によりますが、一般的に2年前後の治療期間となります。
通院回数は、治療段階によりますが、通常2〜3ヶ月に1回です。
【副作用・リスク】
装着時間が少ないと治療期間が長引く可能性があります。
他の矯正治療法と同様に、疼痛・歯根吸収・歯肉退縮の可能性や適切な保定をしないと治療後に後戻りすることがあります。
【医薬品医療機器等法(薬機法)に関する記載事項】
・インビザライン完成物は、日本国内において薬機法未承認の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
尚、インビザラインの材料自体は、日本の薬事認証を得ています。
・「インビザライン」は米国アライン・テクノロジー社の製品の商標であり、インビザリアン・ジャパン社から入手しています。
・日本国内においては、同様の医療機器が薬事認証を得ています。
・インビザライン・システムは、世界100カ国以上の国々で提供され、これまでに900万人を超える患者さまがが治療を受けています。(2020年10月時点)